
来てくださった皆様、ありがとうございました。明日は投票日。四登なつきをどうぞ宜しくお願い致します。
佐久市議会議員

来てくださった皆様、ありがとうございました。明日は投票日。四登なつきをどうぞ宜しくお願い致します。
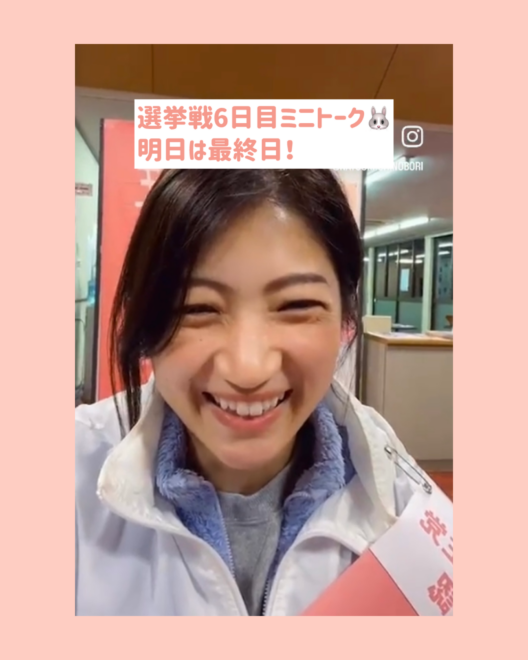
https://youtu.be/x1Xbj8pee58?si=EulOv_vV6C3mUjds
今日は期日前投票行ってきたよとお声がけ下さる方々が😭佐久市議選、明日は最終日です!最後までご声援を頂けますと幸いです。

ぜひ、お越しください!佐久市議会議員選挙最終日です。
こんにちは!選挙戦4日目。柳田佐久市長のスペースで色々とお話しせて頂きました。
・被災地での仕事から変わった価値観
・なぜ、佐久市議か
・アフリカでの経験
・安芸高田市のこと
・私の中の国際教養大学の存在
・4/12玉木雄一郎が佐久平駅に!
ぜひお聞き&シェアください✨
https://x.com/seiji_ya/status/1909854692504686898?s=46
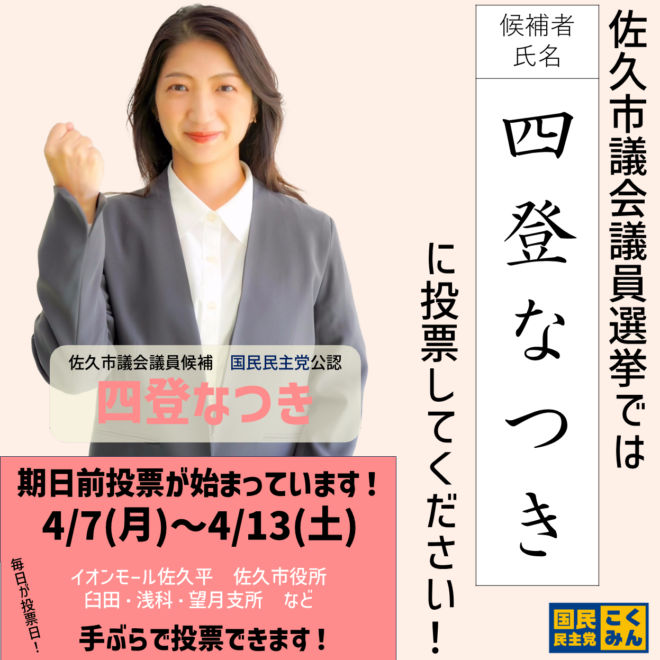
イオンモール佐久平で期日前投票に行ってきました!
投票券も身分証もいりません。お仕事帰り、お買い物の際にふらっとお寄りください。手ぶらでGO!
四登なつきにはあなたの一票が必要です。
選挙戦ミニトークyoutube🐰期日前投票に行ってきました。
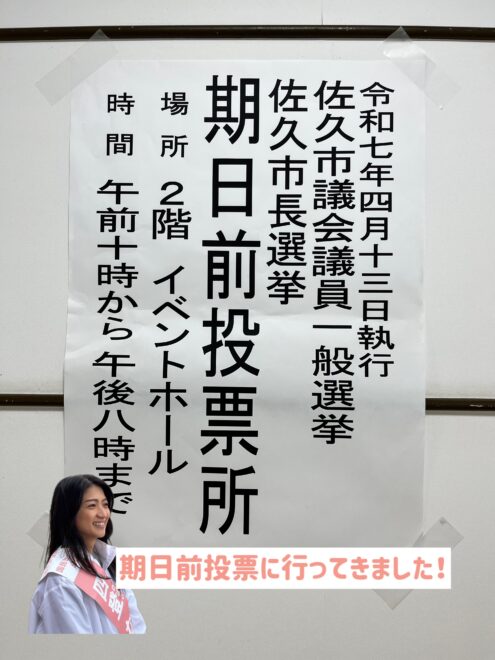
 佐久市議会議員選挙が始まりました。7日間、駆け抜けます!
佐久市議会議員選挙が始まりました。7日間、駆け抜けます!
下記で本日7日から投票が可能です。詳しくはHPへ。四登なつきを宜しくお願いします!
https://www.city.saku.nagano.jp/shisei/senkyo/giin_sityou_senkyo/r7sigisityousenkyo.html#cms36145
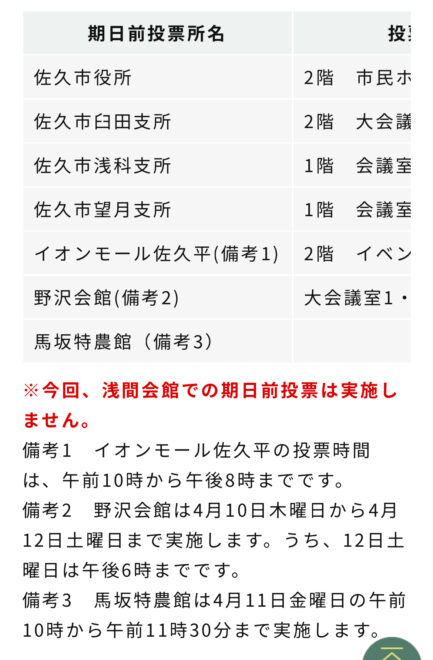
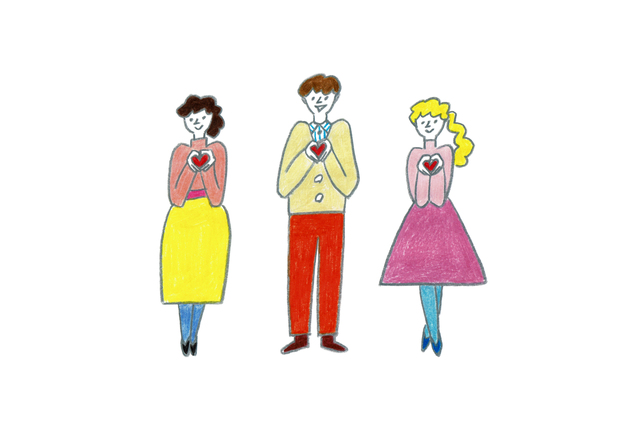
今回の選挙戦で訴えている基本政策の一つが、「地域でこどもを育む「まち」へ」。
※「街」も、「町」も地域の多様性がある佐久市を表す漢字としてしっくりこず、今回は「まち」という表現にしました。
両親共働きでこどをも育てるということが、佐久市でも珍しくはありません。子育てが負担にならないように、実家が近くになくても地域の誰かを頼ることができる、そんな環境を整えていきたいです。
しかし、これは子育て世代のためだけの施策ではありません。
地域でこどもを育むまちは、孤独を抱えないまち。
一般的に、ご高齢の方の3人に1人は社会とのつながりがないと言われています。
成人の8人に1人が潜在的うつ状態の可能性があるというデータもあります。
長野県内の若者の自殺率は全国でも最上位にあります。
佐久市も、何かをきっかけに、孤独を抱えやすい地域なのだと思います。
それは定年退職かもしれない。介護や育児などの家庭の事情かもしれない。会社や学校などの所属する場所での人間関係かもしれない。そんなときに、第三の居場所をもっているかどうかで、その先の進路が変わってきます。
例えば村落支援制度の活用をすすめ、「地域のおせっかい役」を仕組化する。
例えば区のあり方をタップデートし、子育て世代が参加しやすくする。
例えば佐久市に登録している防災士が、防災を切り口に地域の皆さんを繋ぐ。
今ある制度を少し工夫するだけで、できることはたくさんあると考えています。
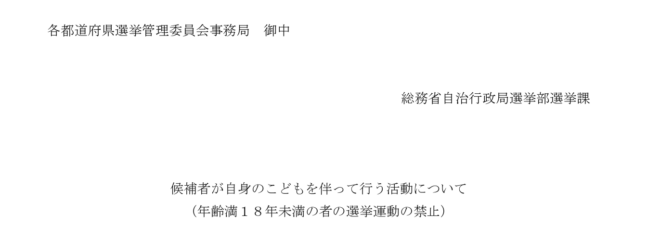
候補者が自身のこどもを伴って行う活動および年齢満18年未満の者の選挙運動について、令和5年に総務省から下記通知があり、実施できるものが整理されました。
◎候補者が自身のこどもを伴って行う活動について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000865536.pdf
18歳未満が実施可能な作業は下記に記載があります。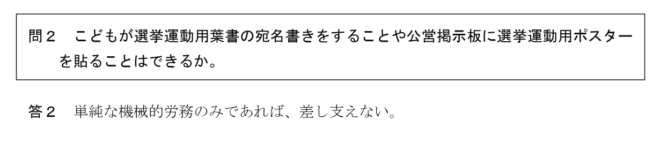
なんと、選挙ポスターがこどもでも貼れるように!!
本当に少しずつですが、子育てしながらの出馬の環境が整理されていっています。
川辺の掃除をしながらいろいろと議論。農業支援のあり方、お墓のあり方、コミュニティとは、自律性を育むにはこどもにどのような機会提供が必要か、などなど。あっという間の時間でした!
千曲川を愛する会の皆様、ありがとうございました✨